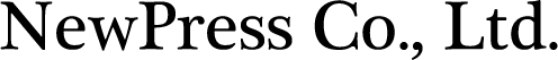BLOG 代表ブログ一覧
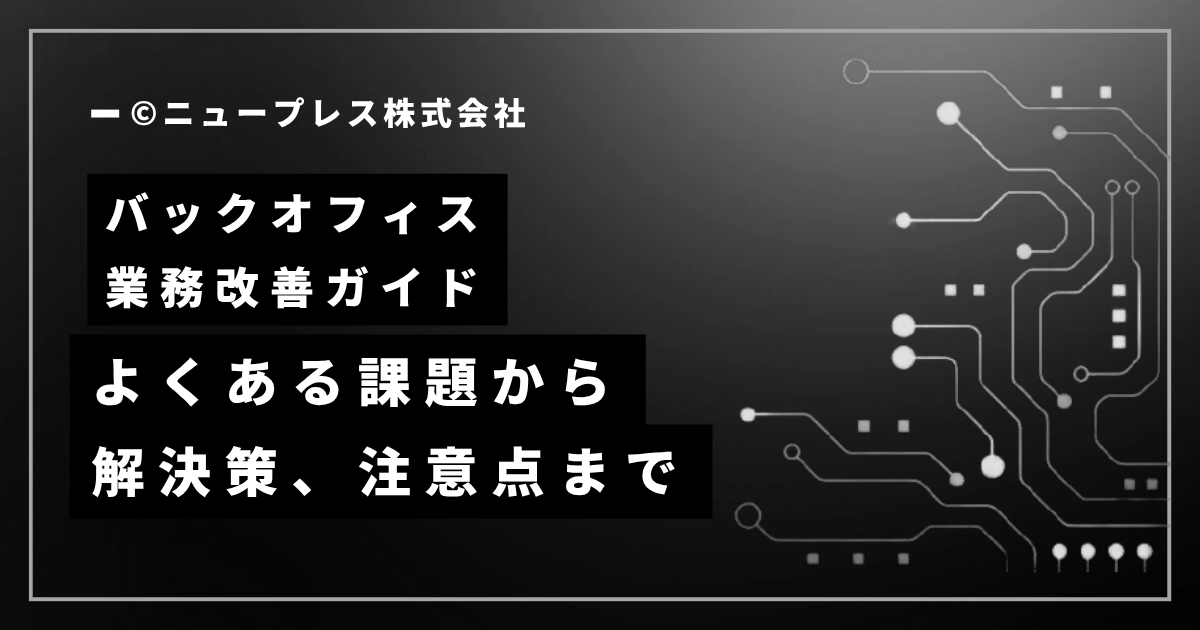
バックオフィス業務改善ガイド|よくある課題から解決策、注意点まで
あなたの会社のバックオフィス、疲弊していませんか?
人手不足、紙業務の多さ、DXの遅れ…。
これらは多くの企業が抱える共通の悩みです。
しかし、これらの課題を放置することは企業の成長を妨げる大きなリスクとなります。

この記事ではバックオフィス業務の改善を成功に導くための具体的なステップと、陥りがちな失敗を避けるためのポイントを解説します。
そもそもバックオフィスとは?

企業の活動は顧客と直接向き合い売上を生み出す「フロントオフィス」の活躍によって成り立っていると思われがちです。
しかし、そのフロントオフィスが本来の力を最大限に発揮するためには後方から組織を支える「バックオフィス」の存在が欠かせません。
バックオフィスはいわば企業成長を支える「守りの要」であり、その役割と重要性を理解することが業務改善の第一歩となります。
バックオフィスの主な業務内容
バックオフィスとは経理、人事、総務、法務、情報システムなど、基本的にお客様と直接関わることのない部門や業務の総称です。
これらの部門は企業活動の根幹である「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源を管理し、組織全体が円滑に機能するための基盤を整える役割を担っています。
- 経理・財務: 請求書の処理、経費精算、決算業務、資金管理など、会社のお金に関わるすべてを扱います。
- 人事・労務: 採用活動、人材育成、給与計算、社会保険の手続きなど、従業員が安心して働ける環境を整えます。
- 総務: 備品管理、オフィスの環境整備、社内規定の作成、株主総会の運営など、他部門が担当しない幅広い業務を引き受けます。
- 法務: 契約書のリーガルチェックやコンプライアンス体制の構築など、企業の法的リスクを管理します。
- 情報システム: 社内システムの運用・保守、セキュリティ対策など、企業のITインフラを支えます。
フロントオフィスとの違いと連携の重要性
バックオフィスの対義語が営業やマーケティング、カスタマーサポートといった顧客と直接やり取りする「フロントオフィス」です。
フロントオフィスが企業の「攻め」を担い売上を拡大する部門だとすれば、バックオフィスは「守り」を固め、その活動を支える部門と言えます。
この両者は決して独立しているわけではありません。
例えば、営業担当者が新しい契約を結んでも、法務の契約書チェックや経理の請求処理が滞れば、ビジネスは前に進みません。
逆に、バックオフィスが業務を効率化し、正確なデータを提供できれば、フロントオフィスはより戦略的な活動に集中できます。
攻めと守りの両輪がスムーズに連携してこそ、企業は継続的に成長できるのです。
あなたの会社は大丈夫?バックオフィスによくある5つの課題
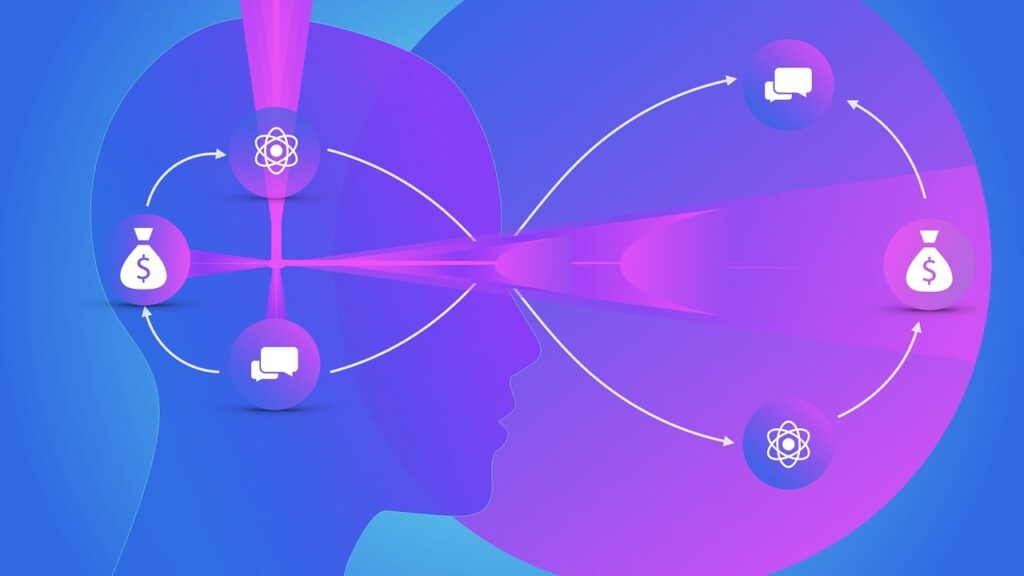
多くの企業がバックオフィス業務において共通の課題を抱えています。
自社の状況と照らし合わせながら、どのような課題が存在するのか、より深く掘り下げて確認してみましょう。
課題1:【非効率】いまだに残る「紙・ハンコ・手作業」の文化
経費精算のために一枚一枚領収書を台紙に貼り、申請書を手書きで作成する。
稟議書を印刷し、承認者の席まで直接持って行ってハンコをもらう。
承認者が不在であれば、その承認の工程は完全に止まってしまいます。
この「紙とハンコ」を中心とした業務のやり方は印刷代や郵送費、書類を保管するためのキャビネットや倉庫の費用といった直接的なコストを生むだけではありません。
書類を探す時間、承認を待つ時間、手作業でのデータ入力にかかる時間など、従業員の貴重な時間を奪い、企業全体の生産性を大きく低下させる原因となっています。
課題2:【属人化】「あの人しか分からない」業務がブラックボックスに
「この複雑な給与計算はAさんしかできない」「月末の特殊な請求書発行はBさんのやり方でないとダメだ」。
このように、特定の業務が個人の経験や知識に依存してしまう「属人化」はバックオフィス部門が抱える根深い課題です。
担当者自身に悪気はなくても、マニュアルが整備されていなかったり、業務のやり方が複雑すぎたりすることで他の人が手を出せないのです。
これでは担当者が急に休んだり、退職してしまったりした場合に、業務が完全に停止するリスクを常に抱えることになります。
業務内容がブラックボックス化するため、非効率なやり方が長年改善されない、ミスや不正が起きても気づきにくいといった問題にも繋がります。
課題3:【人手不足】慢性的な人員不足と一人あたりの業務過多
少子高齢化の影響を受け、多くの業界で人手不足が叫ばれていますが、バックオフィス部門も例外ではありません。
むしろ、直接利益を生み出す部門ではないという考えから、人員補充の優先順位が低くされがちで、慢性的な人手不足に陥っている企業は少なくありません。
その結果、残された従業員一人ひとりの業務負担が増大します。
日々の業務に追われるあまり、業務改善に取り組む時間的な余裕も精神的な余裕もなくなります。
残業が常態化すれば、従業員の心身の健康が損なわれ、最悪の場合、離職にも繋がりかねません。
そうなると、さらに人手不足が悪化するという悪循環に陥ってしまいます。
課題4. 【DXの遅れ】テレワークに対応できず、働き方改革が進まない
政府主導で働き方改革が推進され、多くの企業でテレワークが普及しました。
しかし「契約書に押印するためだけに出社する」「紙で届いた請求書を処理するために、誰かが必ずオフィスにいなければならない」といった理由でバックオフィス部門だけがテレワークを導入できない、あるいは形骸化しているケースが後を絶ちません。
このような状況は従業員の柔軟な働き方を阻害するだけでなく、企業の採用競争力にも悪影響を及ぼします。
より良い労働環境を求める優秀な人材は、柔軟な働き方ができる企業へと流出してしまいます。
課題5:【情報散在】社内問い合わせが多く、本来の業務に集中できない
「最新の経費精算のマニュアルはどこにある?」「この申請書のフォーマットは古くない?」といった問い合わせに、バックオフィスの担当者が日々多くの時間を費やしています。
原因は社内の情報やナレッジがファイルサーバーや社内ポータル、個人のPCの中など、さまざまな場所に散らばってしまっていることです。
情報が整理されていないため、従業員は自力で答えを見つけることができず、バックオフィス部門に質問が集中します。
問い合わせる側も探す手間で時間を浪費し、対応するバックオフィス担当者も、何度も同じ説明を繰り返すことで疲弊し、本来注力すべき専門的な業務に集中できなくなってしまうでしょう。
課題放置はもったいない!業務改善がもたらす4つの大きなメリット

バックオフィス業務の課題を放置することは企業の成長を妨げるだけでなく、さまざまなリスクをはらんでいます。
逆に、これらの課題を解決し、業務改善を実現すれば、企業は多くのメリットを手にすることができるでしょう。
メリット1:コスト削減と生産性の向上
業務改善によって得られる最も直接的なメリットはコスト削減と生産性の向上にあるでしょう。
例えば、紙の書類を電子化することで印刷代や郵送費、保管スペースといった物理的なコストの削減が可能です。
また、手作業で行っていたデータ入力を自動化すれば、作業時間は大幅に短縮され、人件費の抑制にも繋がります。
こうして創出された時間はより付加価値の高い業務に充てられるようになり、企業全体の生産性を高めるのです。
メリット2:ヒューマンエラーの防止と業務品質の安定
手作業によるデータ入力や転記作業は、どれだけ注意深く行ってもミスを完全になくすことは困難なものです。
特に、給与計算や請求処理など、金額を扱う業務でのミスは従業員や取引先からの信頼を損なう原因となり得ます。
業務改善によってこれらの定型作業を自動化・仕組み化すれば、ヒューマンエラーの大幅な削減が期待できるでしょう。
業務のやり方も標準化されるため、担当者による品質のばらつきがなくなり、業務品質全体の安定化が図れます。
メリット3:従業員満足度の向上と優秀な人材の定着
長時間労働や非効率な業務は従業員のモチベーションを低下させ、心身の疲弊を招く一因です。
業務改善によって無駄な作業や待ち時間が削減されれば、従業員はより創造的で付加価値の高い仕事に集中できるようになるでしょう。
また、テレワークなどの柔軟な働き方が可能になることはワークライフバランスの向上にも繋がります。
働きやすい環境は従業員の満足度を高め、優秀な人材の離職を防ぎ、新たな人材を惹きつける魅力となるのです。
メリット4:ガバナンス強化と変化に強い組織体制の構築(BCP対策)
業務の属人化やブラックボックス化は不正行為やコンプライアンス違反の温床となりかねません。
業務改善によって業務のやり方を可視化・標準化することは内部統制の強化となり、健全な組織運営の実現に不可欠です。
さらに、書類の電子化やクラウドシステムの導入は災害やパンデミックといった不測の事態に備える事業継続計画(BCP)としても有効でしょう。
オフィスに出社せずとも事業を継続できる体制は変化の激しい現代において、企業の重要な競争力となるのです。
【実践編】バックオフィス業務改善を成功に導く5ステップ
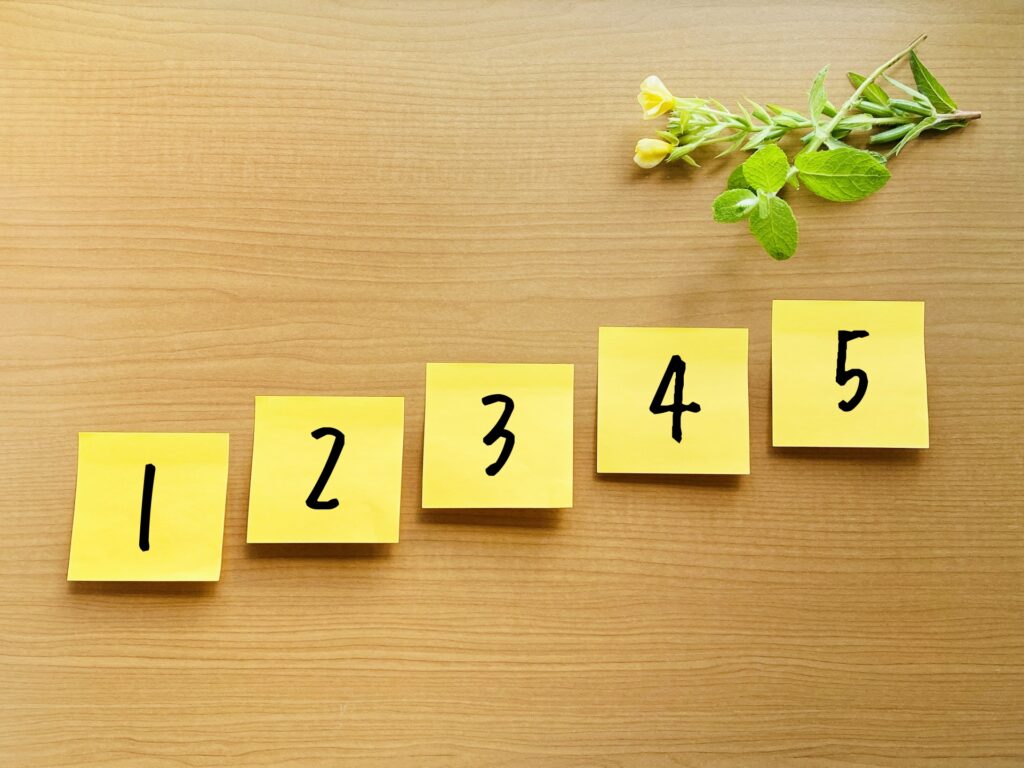
バックオフィス業務の改善は、やみくもに進めても期待した効果は得られません。
成功のためには現状を正しく理解し、計画的に取り組むことが重要です。
ここでは改善を成功に導くための具体的な5つのステップを紹介します。
ステップ1:【現状把握】まずは業務の「棚卸し」から始める
改善の第一歩は現在行われている業務を正確に把握することから始まります。
「誰がいつ、何を、どのように、どれくらいの時間をかけて」行っているのかを、一つひとつ洗い出していくのです。
この「業務の棚卸し」を行うことでこれまで見えていなかった課題や非効率な点が明らかになります。
例えば「請求書の発行」という一つの業務でも「データの抽出」「フォーマットへの入力」「上長による確認」「押印」「封入」「郵送」といった細かい工程に分解できます。
それぞれの工程にかかる時間や担当者を書き出すことでどこにボトルネックがあるのかが可視化されるでしょう。
現場の担当者へのヒアリングは、実態を正確に知る上で欠かせません。
ステップ2:【目標設定】「何を」「どこまで」改善するのかを明確に
現状の課題が明らかになったら、次に取り組むべきは具体的な目標設定です。
「効率化する」「コストを削減する」といった漠然とした目標では、どのような手段を選ぶべきか判断が難しく、後から効果を測ることもできません。
目標は誰が見ても達成できたかどうかが判断できるよう、具体的かつ測定可能なものにすることが肝心です。
「月末の締め作業にかかる時間を2営業日短縮する」「紙の印刷枚数を半年で50%削減する」といったように、数値を用いて設定するのが理想的です。
明確なゴールがあることで関係者の意識が統一され、改善への取り組みがぶれることなく進みます。
ステップ3:【改善策の検討】自社に合った解決策を見極める
課題を把握し、目標が定まったら、いよいよ具体的な解決策の検討に入ります。
解決策にはITツールの導入や業務のアウトソーシングなど、さまざまな選択肢が存在します。
ここで重要なのは自社の規模や予算、企業文化に合った方法を選ぶことです。
例えば、定型的な入力作業が多いのであればRPA(業務自動化ツール)が有効かもしれませんし、専門的な知識が必要な業務であれば、外部の専門業者に委託する方が効率的な場合もあるでしょう。
初期費用だけでなく、運用にかかるコストや、導入によって得られる長期的なリターンも考慮に入れ、多角的な視点で最適な解決策を見極める必要があります。
ステップ4:【導入・実行】スモールスタートで着実に進める
完璧な計画を立てて、一気に全部門へ展開しようとすると、予期せぬ問題が発生した際に大きな混乱を招きかねません。
業務改善はまず特定の部門や影響範囲の大きい一部の業務に絞って始める「スモールスタート」が賢明です。
小さな範囲で試すことで課題や改善点を早期に発見でき、大きな失敗を未然に防げます。
また、小さな成功体験を積み重ねることで現場の従業員のモチベーションを高め、全社的に展開する際の協力も得やすくなるでしょう。
新しいやり方を導入する際は、現場の担当者への丁寧な説明やトレーニングの機会を設けることが鍵となります。
ステップ5:【効果測定】やりっぱなしにせず、効果を測定し次へ繋げる
業務改善は一度きりのイベントで終わらせてはいけません。
施策を実行した後は必ずその効果を測定し、次のアクションに繋げるというサイクルを回し続けることが大切です。
効果測定はステップ2で設定した目標が達成できたかどうかを基準に行います。
削減できた時間やコスト、ミスの発生率といった定量的なデータに加え「業務が楽になったか」「他の業務に集中できるようになったか」といった従業員からの定性的なフィードバックも集めましょう。
期待した効果が出ていれば、その取り組みを他の業務にも展開します。
もし効果が不十分であれば、その原因を分析し、改善策を練り直すのです。
この地道な繰り返しこそが継続的な業務改善に繋がります。
自社に合った方法はどれ?主な業務改善策と選び方のポイント

バックオフィス業務の改善にはさまざまなアプローチがあります。
自社の課題や状況に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。
ここでは代表的な3つの改善策と、それぞれの選び方のポイントを解説します。
方法1:ITツール・システムの導入(RPA、SaaSなど)
手作業による定型業務の多さや、情報共有の非効率性に課題を感じている場合に有効なのがITツールやシステムの導入です。
- RPA (Robotic Process Automation):データ入力や転記、定型的なメール送信など、決まった手順の繰り返し作業を自動化するツールです。ヒューマンエラーを削減し、24時間365日稼働できるため、大幅な生産性向上が見込めます。
- SaaS (Software as a Service):クラウド上で提供されるソフトウェアで会計、人事、勤怠管理、経費精算など、特定の業務に特化したサービスが数多く存在します。自社でサーバーを構築する必要がなく、比較的低コストで導入できるのが特徴です。
【選び方のポイント】
まずはどの業務の、どのような課題を解決したいのかを明確にすることが重要です。
「みんなが使っているから」という理由だけで導入すると、使われないツールになってしまう可能性があります。
従業員が直感的に使えるかどうかも大切なポイントです。
無料トライアルなどを活用し、実際に操作性を試してみましょう。
また、導入後のサポート体制が充実しているかどうかも確認が必要です。
不明点があった際に、すぐに相談できる窓口があると安心です。
方法2:アウトソーシング(業務委託)の活用
専門的な知識が必要な業務や、ノンコア業務に多くのリソースを割かれている場合に有効なのがアウトソーシング(業務委託)です。
- 給与計算・労務手続き:専門知識が必要で法改正への対応も求められる業務です。専門の業者に委託することで正確かつ効率的に処理できます。
- 経理代行:記帳代行や請求書発行、支払い管理などを委託します。月次の締め作業や決算業務の負担を軽減できます。
- 問い合わせ対応:社内外からの電話やメールでの問い合わせ対応を委託します。担当者が本来の業務に集中できる環境を作ります。
【選び方のポイント】
- 業務範囲の明確化:どこまでの業務を委託するのか、事前に明確に定義しておくことが重要です。曖昧なまま依頼すると、期待した効果が得られない場合があります。
- セキュリティ体制:個人情報や機密情報を扱うため、委託先のセキュリティ体制は必ず確認しましょう。プライバシーマークやISMS認証などを取得しているかどうかが一つの目安になります。
- 実績と専門性:自社と同じ業種や規模の企業での実績が豊富か、専門的な知識を持ったスタッフが在籍しているかを確認しましょう。
方法3:外部の専門家と協力して進める
「何から手をつければいいか分からない」「社内に業務改善を推進できる人材がいない」といった場合には外部の専門家の力を借りるのも有効な選択肢です。
コンサルタントや専門サービスは客観的な視点から自社の課題を分析し、最適な解決策を提案してくれます。
また、ツール導入やアウトソーシングの選定、社内への導入支援まで一貫してサポートしてくれる場合もあります。
選び方のポイント
- 得意領域の確認:業務改善とひとくちに言っても、コンサルタントによって得意な領域はさまざまです。自社の課題に合った専門性を持っているかを確認しましょう。
- コミュニケーションの相性:業務改善は社内のさまざまな部署と連携しながら進める必要があります円滑なコミュニケーションが取れるか、信頼関係を築けそうかといった相性も重要です。
- 支援の範囲:どこまでサポートしてくれるのか、事前に明確にしておきましょう。課題分析だけなのか、実行支援まで行うのか、その後のフォローはあるのかなど、具体的な支援内容を確認することが大切です。
【要注意】これだけは避けたい!バックオフィス業務改善のよくある失敗例
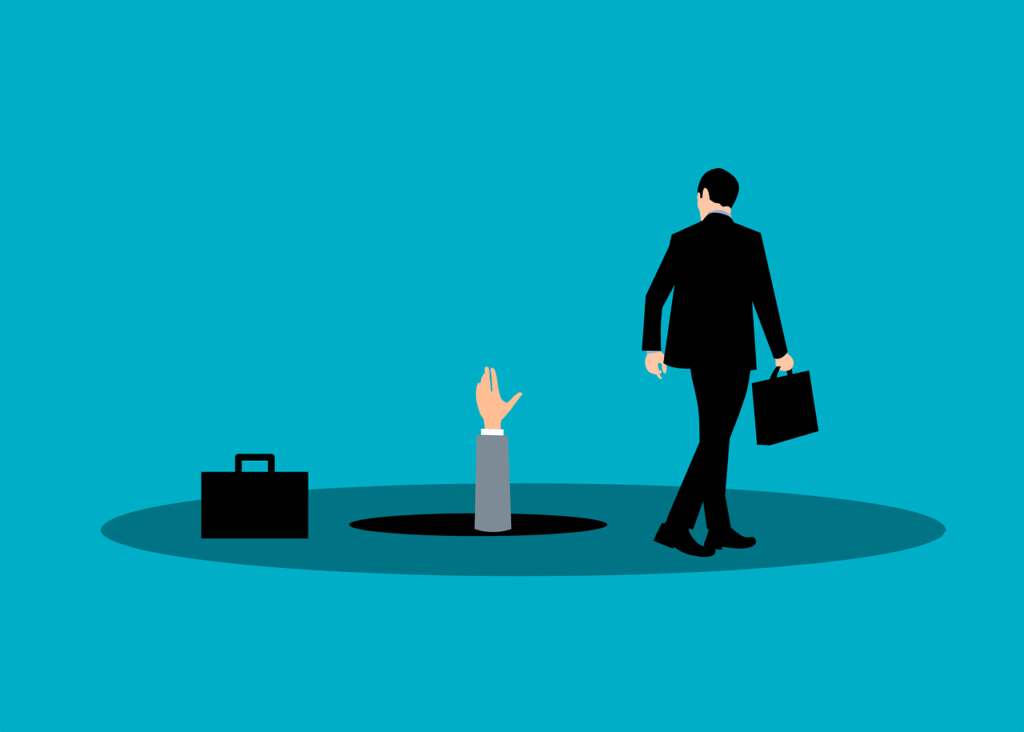
バックオフィス業務の改善は時間もコストもかかる取り組みです。
しかし、良かれと思って進めた施策がかえって現場の混乱を招いたり、効果が出ずに終わってしまったりするケースも少なくありません。
ここではそうした失敗を避けるために知っておきたい、よくある3つの失敗例とその対策を解説します。
失敗例1:目的が曖昧なまま「とりあえずツール導入」に走ってしまう
「DXが流行っているから」「競合他社が導入したから」といった理由で目的が明確でないままITツールを導入してしまうのは典型的な失敗パターンです。
「何のために導入するのか」「導入して何を解決したいのか」が曖昧なため、どのツールが自社に最適か判断できず、機能を持て余したり、逆に機能が足りなかったりします。
結果として、現場の従業員は使い方を覚えられず、結局元のやり方に戻ってしまい、高額な導入費用が無駄になりがちです。
対策方法
まずは前述のステップ1、2で解説したように、現状の業務を棚卸しし、課題を明確にすることから始めましょう。
「誰の、どの業務の、どんな課題を解決したいのか」を具体的に定義することで初めて自社に必要なツールの要件が見えてきます。
失敗例2:現場の意見を聞かずに進めてしまい、形骸化する
経営層や情報システム部門がトップダウンで導入するツールや新しい業務のやり方を決めてしまい、実際にそれを使う現場の従業員の意見を聞かないケースも、失敗に繋がりやすいパターンです。
現場の実態に合わないツールやフローはかえって業務を煩雑にし、従業員の負担を増やすことになりかねません。
結果として「新しいやり方は面倒だから」と使われなくなり、せっかくの改善策が形骸化してしまいます。
対策方法
業務改善の主役はあくまで現場の従業員です。
計画の初期段階から現場の担当者を巻き込み、ヒアリングや意見交換の場を設けましょう。
実際にツールを試してもらい、フィードバックをもらうことも重要です。
現場の納得感を得ることがスムーズな導入と定着の鍵となります。
失敗例3:「導入して終わり」で効果測定や改善が行われない
ITツールを導入したり、アウトソーシング先を決定したりしたことで満足してしまい、その後の効果測定や改善活動を行わないケースもよく見られます。
導入したツールが本当に業務効率化に繋がっているのか、委託した業務の品質は担保されているのかを定期的に評価しなければ、問題点に気づくことができません。
また、ビジネス環境や社内の状況は常に変化するため、一度決めたやり方がいつまでも最適とは限りません。
対策方法
ステップ5で解説したように、導入後は必ず効果測定を行いましょう。
削減できた工数やコスト、エラー率の変化などを定量的に評価するとともに、従業員へのアンケートなどで定性的な効果も把握します。
その結果をもとに、ツールの設定を見直したり、アウトソーシング先との連携方法を改善したりと、継続的にPDCAサイクルを回していくことが重要です。
まとめ
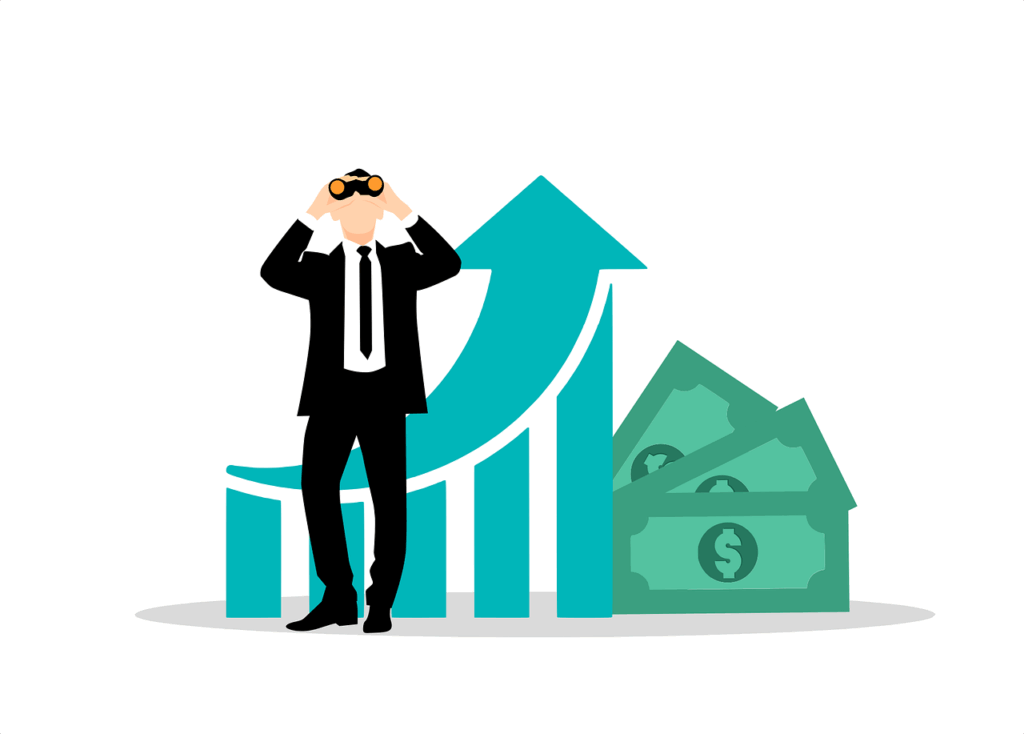
バックオフィス業務改善の効果はただのコスト削減や効率化だけではありません。
従業員の働きがいを高め、生産性を向上させ、変化に強い組織体制を築くための重要な経営戦略です。
本記事ではバックオフィス業務の課題から、具体的な改善ステップ、そして陥りがちな失敗例までを解説してきました。
- バックオフィスの課題: 紙文化、属人化、人手不足、DXの遅れ、情報散在
- 改善のメリット: コスト削減、生産性向上、品質安定、従業員満足度向上、ガバナンス強化
- 成功への5ステップ: ①現状把握 → ②目標設定 → ③改善策の検討 → ④導入・実行 → ⑤効果測定
- 主な改善策: ITツール導入、アウトソーシング、専門家との協力
- 失敗を避けるポイント: 目的の明確化、現場との連携、継続的な改善
これらのポイントを押さえ、自社の状況に合った方法で改善を進めることが成功の鍵となります。
まずは本記事で紹介した内容を参考に、自社のバックオフィス業務を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。
【宣伝】AI活用で、貴社のバックオフィスは生まれ変わります
弊社ではお客様ごとにカリキュラムを作成し、その会社に最適なオリジナルの生成AI研修を実施しています!下記ボタンより今すぐチェックしてくださいね。
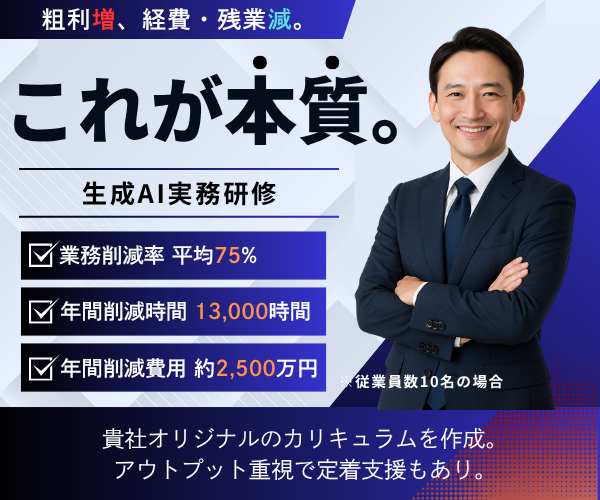
05
CONTACT
お問い合わせ
ご質問やお見積もり、協業依頼などなんでもお気軽に連絡ください。